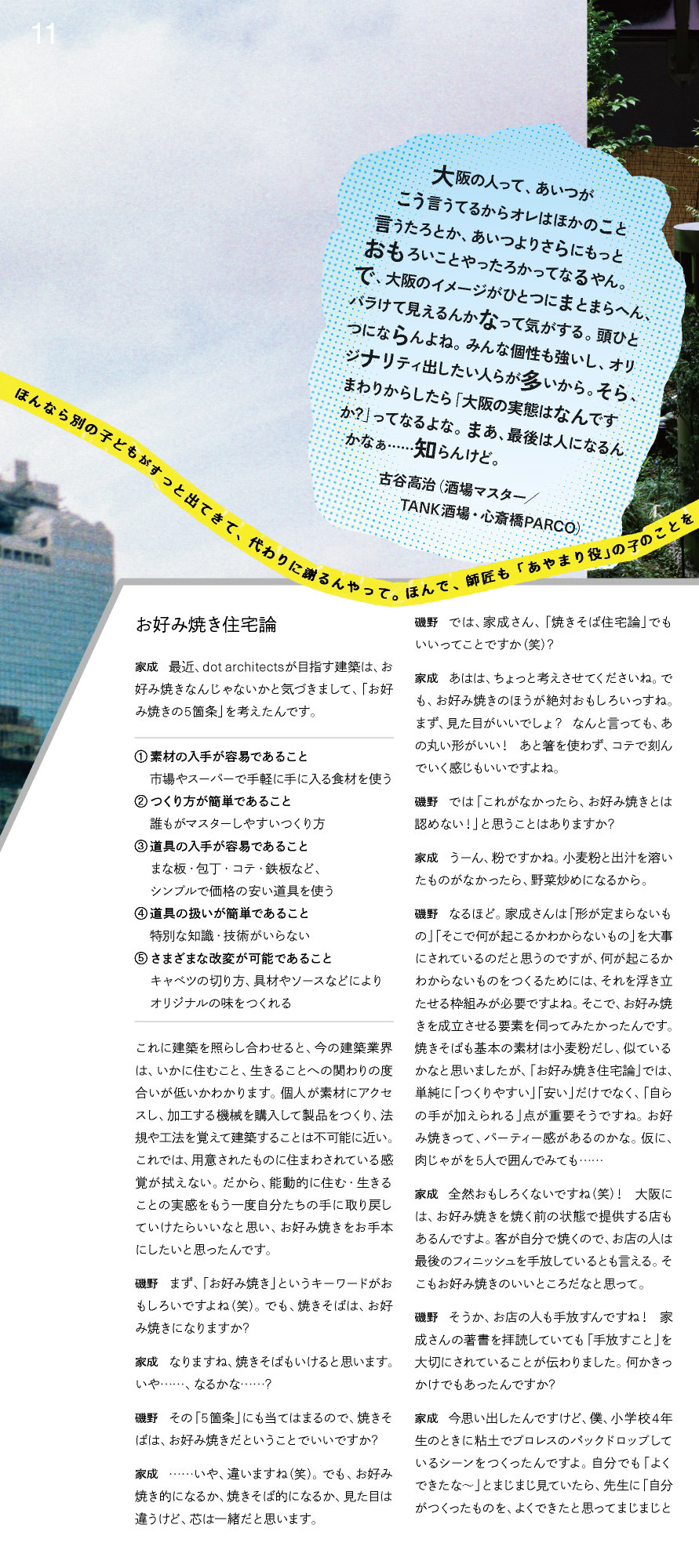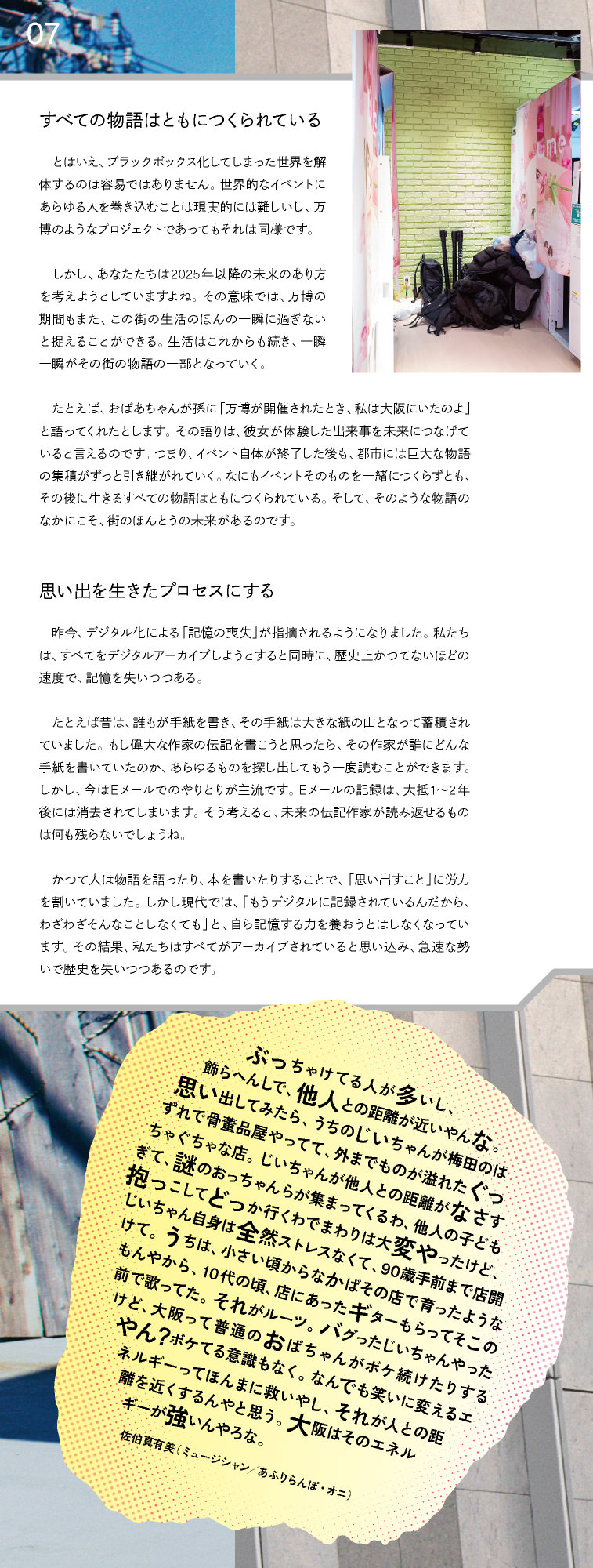生きた世界の住人として、
ともにつくること
日々のささやかな営みから、他者や動植物、自然環境との関わりまでをひとつらなりで捉え、私たちの暮らしと社会について考えることはできないか。考古学・芸術・建築と人類学の交差点で思索する人類学者ティム・インゴルドさんに聞く、身のまわりの物事に耳を傾け、ともにつくること。
- 収録:
- 2022年2月25日オンラインにて
- 聞き手:
- 齋藤精一[Expo Outcome Design Committee/Panoramatiks主宰]
人生は続くこと、それ自体に意味がある
「世界はあまりに加速しすぎているから、スローダウンする必要がある」とよく言われますが、個人的には少し違うように思います。仮にあらゆる物事をスローモーションにしても、問題は解決しないのではないでしょうか?
「この計画には、何年の月日がかかる」「あれをつくるために、これくらい時間をかけよう」など、私たちはどうしても、すべての行動を目標に向かう時間に置き換えてしまいます。大切なのは、この思考から脱却することです。つまりは「輸送(Transport)」から「徒歩旅行(Wayfaring)」への変化。「目標を掲げて、AからBへ移動すること」から「常にまわりの状況に反応し続けられる状態にあること」への転換こそがほんとうのシフトだと考えています。
何年も前、人類学のフィールドワークで、トナカイを飼うサーミ人たちと一緒に仕事をしたことがありました。そこでは長いあいだ何もすることなく、ただトナカイを見守り続けるんですね。でも、ひとたび風向きや天候などすべての条件がちょうど整う瞬間が訪れると、トナカイの群れを一気にまとめ上げ、素早く行動する。
私たちの行動は、すべて人生の一部であると捉えてみましょう。そもそも人生には、目的なんてない。人生は続くこと、それ自体に意味があるのです。
世界は共有するもの
未来について考えようとするとき、私たちはしばしばテクノロジーをたよりにしてしまいます。でも、それは「未来を問うことは、テクノロジーについて考えることだ」と思い込んでいるからかもしれません。
デジタルワールドやバーチャルリアリティ、人工知能などに囲まれた世界で、あらゆるもののエンターテイメント化が進んでいます。たとえば、生活者が決して訪れることができないような場所にテレビで人気の科学者を派遣して、野生動物の素晴らしい映像を撮影し、放映する―その結果、私たちは地球上のすべての生物はテレビで眺めるものだと捉えてしまっている。
地球、空、あらゆる生物は、人間の娯楽のために存在しているわけではありません。私たちは「生きた世界の住人(Inhabitants of a living world)」であるという感覚をなんとかして取り戻す必要がある。それは、「世界」をなんらかのパフォーマンスを見せるための単なる舞台として捉えていては、気づけない感覚でもあります。ほかの存在と関わり、ともに生きること。「世界は共有するもの」という視点に立たない限り、未来を考えることは不可能です。

人類はこれまで資源が無限にある限り、科学技術や芸術、創造性は発展し続けると考えてきました。でも私たちは今、資源は有限であると気づいています。未来なき未来につながる「発展」を選ぶのか。生命の継続に専念する「持続可能性」を選ぶのか。その選択を迫られているのだと捉えることもできるでしょう。
持続可能性というと、安定していて変わらない状態を維持し続けるというイメージを持つ方もいるかもしれません。そうではなく、世代を超えて生命と暮らしが続いていくよう絶えず働きかけること。限られた人やある一定の時間にとどまることなく、すべての人、すべてのもの、すべての時間において、ともに生きられる世界をどのように実現するのか。未来を考えるにあたっては、この問いを軸に据えることが大切です。
その手がかりとして、まず親族関係と家族関係、そして出自に着目すること。これは人類学の古典的な手法です。何世代にもわたって、どのように関係が紡がれてきたのか、そして、どのように再生産されていくのかと考えることからはじめるのがよいでしょう。
違いがあるからおもしろく、実りあるものになる
AFTER2025のテーマは「足元から公共を考える」でしたね。「公共(Public)」というと、何か共通の目的によって結ばれ、それを守ろうとする人たちを想像するかもしれません。しかし、私は「ある問いのもとに集う人々のコレクティブ」と捉えています。そして、それぞれの問いに独自の公共性が引き出される。
公共は、「会話(Conversation)」により支えられています。私が考える会話は、ジョン・デューイが公共について記した哲学に基づいています。ポイントは「差異にこそ、意味がある」ということです。
少し想像してみてください。もし、みんながまったく同じ考えを持っていたら、会話は成り立たないと思いませんか? それぞれが違うことを考えていたり、異なる経験や知恵を持ち込むからこそ、私たちは言葉を交わすことができる。人は誰しも異なる経験を持っています。だからこそ、なんらかの形で会話に関わっていくことができる。公共とは、「ある問いに対して集められた異なる経験や知恵の集合」なのです。
これは民主主義についても言えることです。民主主義は今や、民意と同一視され、私たちとそれ以外を分断するものに貶められています。しかし本来の民主主義は、「違い」によって分断されることなく、人々がともに集い会話できるものであるはず。異なる経験や考えを持っているからこそ、私たちの共存はよりおもしろく、実りあるものになる。あらゆる原理主義が台頭するなかで、このことが忘れ去られようとしているのはとても怖いことです。

他者を真剣に受け止める
そんな異なる背景を持つ人たちがともにつくる。そのための鍵は、実は教育にあります。「私たちは、どのように教えたらいいのだろうか」という問いですね。今の教育は、高度に技術化された社会で人々を機能させるべく、必要な知識を次世代に伝達することを目的としています。しかし、それは間違いです。教育とは本来、私たちの人生の歩みを導くこと。固定観念や思い込みから解放し、世界に対する知覚をひらく―私たちは、世界や他者に耳を傾け、目を凝らし、注意を払い、ケアし、対応しながら学ばなければならないのです。
私が人類学はとても重要だと考える理由もその点にあります。人類学は「他者の声に耳を傾け、真剣に受け止めること」を公言している唯一の学問です。人々の経験から発された言葉に学び、私たちみんなの人生の道しるべとする。これこそが人類学の主題であり、社会生活の主題でもあります。このような人類学を実践できれば、違いのなかで共生していくモデルになるかもしれませんね。
デザインとは、外へと溢れ出させること
ともにつくると言っても、なにも誰もがデザインの専門家になる必要はありません。いわば、同じ船をみんなで一緒に漕いでいるようなものですからね。ともにつくるプロセスとはその意味で、人生のプロセスとも言えます。異なる状況に置かれた私たち自身が「どのように生きるべきか」をひもといていく。この問いに答えるには、あらゆる人の助けが必要です。
しかし現在のデザインは、周囲の物事に気を配らずとも滞りなく機能することばかりを重視しています。たとえば、あらゆる電気配線を隠すようなデザインは、スイッチの奥に、生活の仕組みのすべてを隠し、ブラックボックス化してしまう。その結果、消費者は電源のオン/オフを管理するためのインターフェースだけに目を向けることになる。まるでヘッドフォンと耳栓をつけて、周囲の環境を瞬時に察する感覚をシャットアウトしてしまっているようです。
さて、どうすればいいでしょうか。物事を閉じ込めるのではなく、外へ溢れ出させること。そうすることではじめて、私たちの身のまわりで起こることに応答する生き方ができるようになります。

外へと溢れ出させるための方法、そのひとつは動詞化することです。たとえば、コモンズ(共有の資源)を動詞化して、「コモニング(Commoning)」に変えてみるのはどうでしょう? すでに同様のことを提案している人も多くいますが、コモンズをひとつの活動として捉えることで、ある問題のもと、異なる経験と背景を持った人々が集い、会話することができるようになります。
そしてコモニングには、会話を前に進める力がある。一人ひとりが想像力を発揮して、会話を通して、理解し合える場所を見つけ出す―これは、過去を掘り下げて、すべての人たちの共通点に立ち戻ることとは真逆の考え方です。それぞれが自分の経験を軸にしながらも、今いる場所を超えて、想像力を前に向かって投げ出すこと、それこそがコモニングなのです。
すべての物語はともにつくられている

とはいえ、ブラックボックス化してしまった世界を解体するのは容易ではありません。世界的なイベントにあらゆる人を巻き込むことは現実的には難しいし、万博のようなプロジェクトであってもそれは同様です。
しかし、あなたたちは2025年以降の未来のあり方を考えようとしていますよね。その意味では、万博の期間もまた、この街の生活のほんの一瞬に過ぎないと捉えることができる。生活はこれからも続き、一瞬一瞬がその街の物語の一部となっていく。
たとえば、おばあちゃんが孫に「万博が開催されたとき、私は大阪にいたのよ」と語ってくれたとします。その語りは、彼女が体験した出来事を未来につなげていると言えるのです。つまり、イベント自体が終了した後も、都市には巨大な物語の集積がずっと引き継がれていく。
なにもイベントそのものを一緒につくらずとも、その後に生きるすべての物語はともにつくられている。そして、そのような物語のなかにこそ、街のほんとうの未来があるのです。
思い出を生きたプロセスにする
昨今、デジタル化による「記憶の喪失」が指摘されるようになりました。私たちは、すべてをデジタルアーカイブしようとすると同時に、歴史上かつてないほどの速度で、記憶を失いつつある。
たとえば昔は、誰もが手紙を書き、その手紙は大きな紙の山となって蓄積されていました。もし偉大な作家の伝記を書こうと思ったら、その作家が誰にどんな手紙を書いていたのか、あらゆるものを探し出してもう一度読むことができます。しかし、今はEメールでのやりとりが主流です。Eメールの記録は、大抵1〜2年後には消去されてしまいます。そう考えると、未来の伝記作家が読み返せるものは何も残らないでしょうね。
かつて人は物語を語ったり、本を書いたりすることで、「思い出すこと」に労力を割いていました。しかし現代では、「もうデジタルに記録されているんだから、わざわざそんなことしなくても」と、自ら記憶する力を養おうとはしなくなっています。その結果、私たちはすべてがアーカイブされていると思い込み、急速な勢いで歴史を失いつつあるのです。
美しい夕陽を見かけると、すぐにスマートフォンを取り出して、写真を撮ってしまう。時間をかけて眺めたり、誰かに話したりすることもなく、ただ写真を撮ってそれで終わり。まるで、過去をゴミ箱に捨ててしまっているようです。
何か別の方法で記憶を引き出す力を手繰り寄せることはできないでしょうか。しばらく会っていなかった人に偶然出会うと、突然「◯◯年に△△で会った人だ!」と当時のことを思い出すことは誰しも経験があると思います。過去を現在に引き寄せて、未来へとつなげる。思い出を埋め、溜め込むのではなく、生きたプロセスにすることが大切ですね。
いずれにしても、すべてを後世のために記録することはできません。むしろ、そんなことはどうでもよくて、物語が世界のなかで生き続けることが重要です。万博には、きっと何百万人もの人々が訪れ、決して出会うことのなかった人たちがぶつかり、融け合い、記憶や物語を持ち帰るでしょう。そのメルティングポットこそがもっとも価値のあるものだと思います。
人生はおもしろいもの

私は、人生はおもしろいものであるはずだと信じています。この豊かさや喜びが奪われることがどれほど悲惨なことか、ここ数年で痛感しました。少し感傷的に聞こえるかもしれませんが、人生は愉しいものであるべきです。世界にはあまりにも多くの不幸や破壊、皮肉、偏見がある。だから人は人生の豊かさをすぐに忘れてしまう。誰にとってもいいことではありませんよね。
2025年、私は77歳になります。あと何年生きられるでしょうね。ただ、私は特定の期間や日付にはあまり関心がありません。ひとたび大きなイベントを計画したらそれでおしまい。次に考えるのは50年後。これでは意味がありませんよね。
私にとって大切なのは、2025年以降も世界が永遠に続くことです。2025年以前の地球の歴史が、永遠であったのと同じように。人生は続く。一つひとつの年はただの通過点、いわば句読点のようなものなのかもしれません。
ティム・インゴルド|1948年英国バークシャー州レディング生まれの人類学者。トナカイの狩猟や飼育をめぐる、フィンランド北東部のサーミ人の社会と経済の変遷についてフィールドワークを行う。線という観点からあらゆるものを捉え直す『ラインズ 線の文化史』(左右社)、手の仕事を通じて人類学を編み直す『メイキング 人類学・考古学・芸術・建築』(左右社)のほか、『ライフ・オブ・ラインズ 線の生態人類学』(フィルムアート社)、『人類学とは何か』(亜紀書房)、『生きていること』(左右社)などの著書がある。